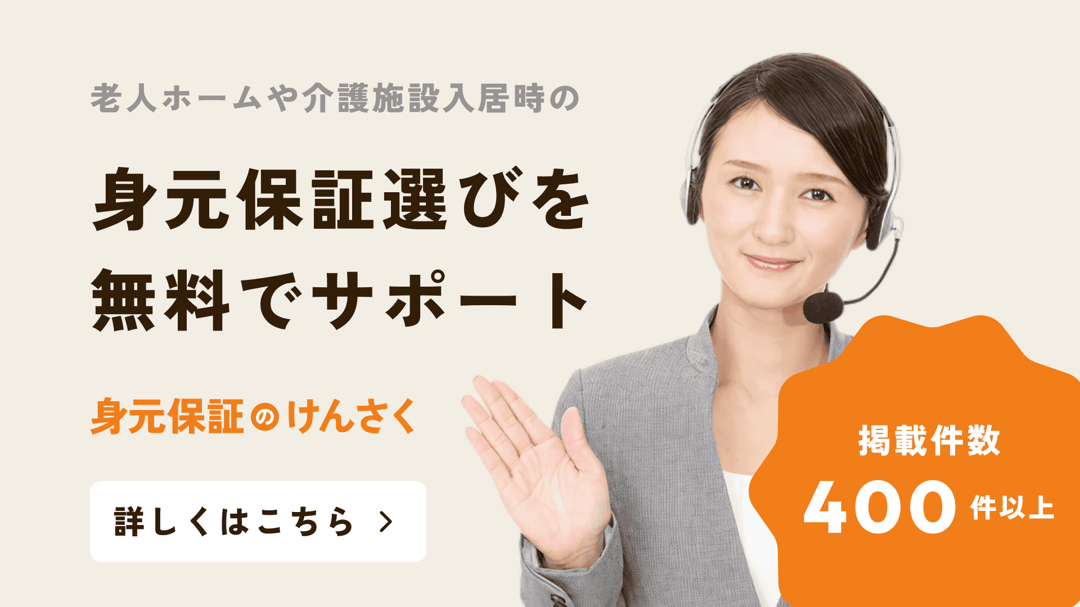.png)
【超入門】要介護認定とは?要支援1・2と要介護1~5の違いを一覧表でわかりやすく解説
更新日: 2025年09月04日
「親の介護申請をしたら、『要介護2』という結果が届いた。でも、これって一体どういう状態なの?」 「そもそも『要支援』と『要介護』って、何がどう違うの?」
介護保険サービスを利用する第一歩、「要介護認定」。その結果通知に書かれた言葉の意味が分からず、戸惑ってしまう方は少なくありません。
ご安心ください。この記事では、介護の必要度を示す全7段階の区分(要支援1〜2、要介護1〜5)について、分かりやすい一覧比較表を使いながら、それぞれの状態の目安と利用できるサービスを、どこよりも簡単にご紹介します!
結論:7段階の要介護認定 早わかり比較表
まずは全体像を掴みましょう。「要支援」は自立した生活を送るための予防、「要介護」は生活を支えるための介助が中心となります。
区分 | 状態のキーワード | 具体的な状態の目安 |
要支援1 | ほぼ自立 | 基本的に一人で生活できるが、立ち座りや掃除などで時々不安定さが見られる。 |
要支援2 | 部分的な支援が必要 | 食事や入浴は自立。立ち上がりや歩行にふらつきが見られ、何らかの支えが必要。家事の一部に支援が必要。 |
要介護1 | 部分的な介助が必要 | 排泄や食事はほぼ自立。立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や着替えなどに一部介助が必要。 |
要介護2 | 軽度の介助が必要 | 食事や排泄にも時々介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要で、入浴や着替えには介助が必要。 |
要介護3 | 中等度の介助が必要 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。食事、排泄、入浴、着替えなど日常生活全般に介助が必要。 |
要介護4 | 重度の介助が必要 | 介助なしでは日常生活を送ることがほぼ不可能。思考力や理解力の低下が顕著に見られる。 |
要介護5 | 最重度の介助が必要 | 寝たきりの状態で、意思の伝達も困難。常時介護が必要。 |
「要支援」と「要介護」の根本的な違いとは?
この2つの大きな違いは、サービスの目的にあります。
- 要支援(1・2): 目的: 介護が必要な状態になることを予防する(介護予防サービス) 状態: 基本的な日常生活は自分でできるが、家事や身支度などで部分的な支援があれば、状態の維持・改善が見込まれる状態。
- 要介護(1〜5): 目的: 日常生活を送る上で必要な介助を提供する(介護サービス) 状態: 基本的な日常生活動作においても、何らかの介助が必要な状態。
【各区分の詳細】どんなサービスが使えるの?
要支援1・2の方が利用できる「介護予防サービス」
生活機能を維持・向上させ、要介護状態になるのを防ぐためのサービスが中心です。
- 介護予防訪問介護/通所介護(デイサービス): ヘルパーさんによる支援や、デイサービスでの機能訓練など。
- 介護予防福祉用具貸与: 手すりや歩行器などのレンタル。
要介護1〜5の方が利用できる「介護サービス」
要介護度が上がるにつれて、利用できるサービスの種類や量(区分支給限度額)が増えていきます。
要介護1・2:在宅生活を支えるサービスが中心
- 訪問介護(ホームヘルプ): 食事や入浴、排泄などの「身体介護」と、調理や掃除などの「生活援助」。
- 通所介護(デイサービス): 施設で食事や入浴、レクリエーションなどを行う。
- 福祉用具貸与: 要介護2から車椅子のレンタルが可能になるなど、利用できる品目が増える。
要介護3・4・5:より手厚い介助と、施設入所が本格的な選択肢に
- 利用できるサービスの量が増加: 訪問介護やデイサービスの利用回数を増やすことができる。
- 特別養護老人ホーム(特養)への入所: 原則として要介護3以上の方が入所対象となるため、これが大きな分岐点になります。
- 介護用ベッドのレンタル: 要介護2以上から可能。
- ショートステイ(短期入所): 家族の休息(レスパイトケア)のためにも、より計画的に利用しやすくなる。
どうやって決まるの?要介護認定の流れ
要介護認定は、以下の4ステップで進められます。
- 申請: ご本人またはご家族が、お住まいの市区町村の窓口(介護保険課など)で申請します。
- 認定調査: 市区町村の調査員が自宅などを訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。同時に、市区町村が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
- 審査・判定: 訪問調査の結果と主治医意見書を元に、専門家で構成される「介護認定審査会」で、どの区分に該当するかが審査・判定されます。
- 結果の通知: 申請から原則30日以内に、認定結果が記載された「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。
まとめ:認定区分は、最適なケアプランを作るためのスタートライン
要支援と要介護、そして7段階の区分。その違いを理解することは、ご本人やご家族がこれからどのようなサポートを受けられるのかを知るための第一歩です。
要支援 | 介護予防が目的。自立した生活を支える。 |
要介護 | 日常生活の介助が目的。暮らしを支える。 |
認定区分は、あくまでもその時点での状態を示す目安です。最も大切なのは、この結果を元に「ご本人が望む生活を、どうすれば実現できるか」を、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターの職員と具体的に話し合っていくことです。
この記事を参考に、ご本人にとって最適な介護サービスを見つけるための一歩を踏み出してください。
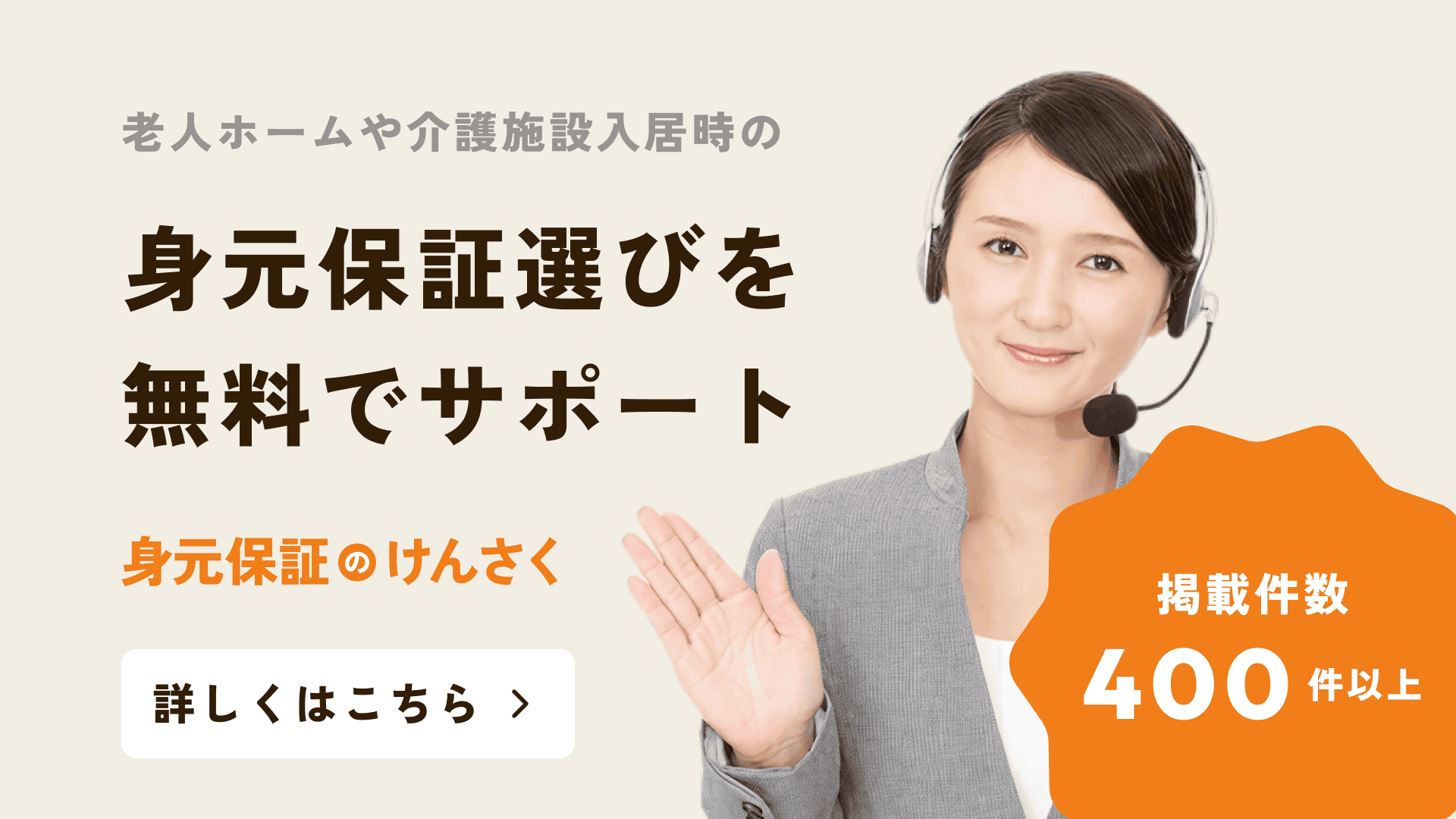
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)