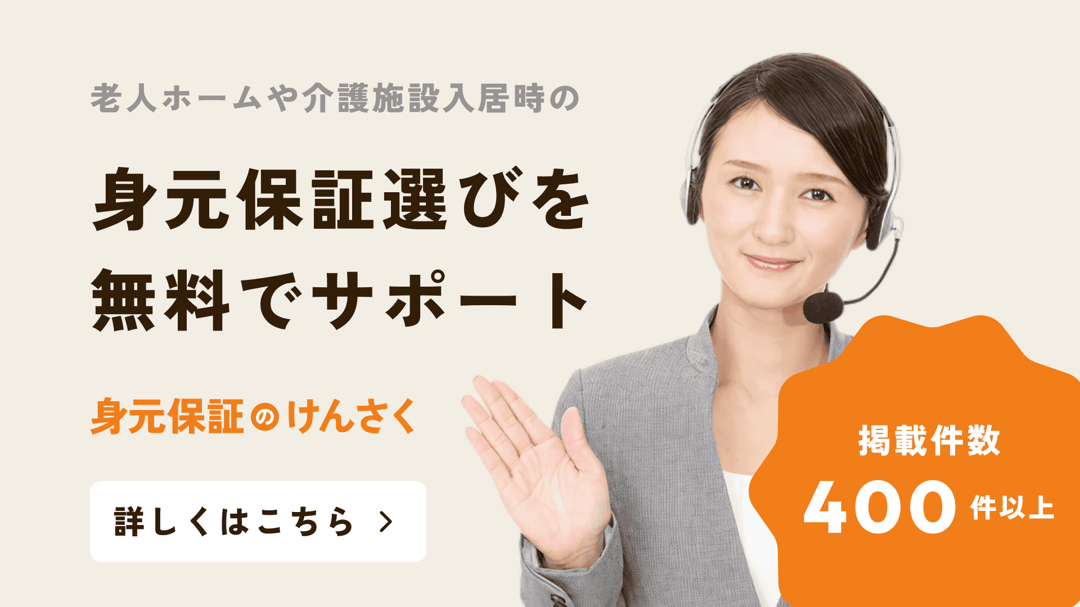.png)
「特別受益」とは?相続で財産をもらいすぎた人への対処法
更新日: 2025年09月10日
相続が発生したとき、特定の相続人が生前に多額の財産を受け取っていた場合、遺産分割をめぐるトラブルに発展することがあります。このときに関係してくるのが**「特別受益」**という概念です。この記事では、特別受益とは何か、そしてどのように対処すればよいのかについて詳しく説明します。
特別受益とは
特別受益とは、相続人の中で特定の人が被相続人(亡くなった人)から、生前に受けた特別な贈与や遺贈のことを指します。
これは、通常の相続とは別に、特定の相続人が「特別に」受け取った利益と見なされます。特別受益があると、遺産分割の際にその分を考慮して、他の相続人との公平を図る必要があります。
- 特別受益の代表例
- 結婚資金や住宅購入資金の援助
- 事業を始めるための資金提供
- 特定の相続人への高額な贈与(車や不動産など)
なぜ特別受益がトラブルになるのか
特別受益は、家族間の公平感を損ない、相続トラブルの大きな原因となります。
1. 不公平感の発生
特別受益を受けた相続人が、他の相続人よりも多くの遺産を受け取ることになると、不公平感が生まれます。これが原因で、家族間の関係が悪化することも少なくありません。
2. 遺産分割協議の難航
特別受益の内容や価値について、相続人間で意見が分かれることが多く、話し合いが複雑化します。具体的な証拠がない場合、感情的な対立に発展し、遺産分割のプロセスが長引くこともあります。
3. 法的トラブルへの発展
相続人間で合意が得られない場合、裁判所に判断を仰ぐことになり、法的な争いに発展するリスクがあります。
特別受益の対処法:持ち戻し計算
特別受益がある場合、民法では「持ち戻し」という方法で公平な遺産分割を図ります。
持ち戻しとは、特別受益として受け取った分を、あたかも遺産に存在するかのように見なして計算することです。
持ち戻しの計算例
- 遺産総額: 1,000万円
- 特別受益: 300万円(ある相続人が生前に受け取った)
- 法定相続人: 2人(特別受益を受けた相続人A、受けなかった相続人B)
- 持ち戻し後の遺産総額を計算: 1,000万円(遺産)+ 300万円(特別受益)= 1,300万円
- 各相続人の法定相続分を計算: 1,300万円 ÷ 2人 = 650万円
- 各相続人の最終的な取り分を計算:
- 相続人A: 650万円 - 300万円(特別受益分)= 350万円
- 相続人B: 650万円
この計算により、特別受益を受けた相続人Aが不当に多くの遺産を受け取ることがないように調整されます。
特別受益に関する注意点
- 遺言書での指定: 被相続人が「持ち戻しをしない」と遺言書で明確に示している場合、特別受益は持ち戻し計算の対象外となります。
- 遺留分との関係: 遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合です。特別受益がある場合、遺留分の計算にも影響を及ぼすため、正確な把握が必要です。
まとめ
特別受益は、相続トラブルの大きな原因になり得ますが、事前の対策や専門家の協力を得ることで、円満な解決が可能です。
- 生前の対策: 贈与契約書や遺言書で、特別受益の有無や内容を明確にしておくと、トラブルを未然に防げます。
- 専門家への相談: 特別受益の有無や価値の評価は複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することが有効です。
- オープンな話し合い: 相続人間でオープンかつ冷静な話し合いを行うことが、感情的な対立を和らげ、合意形成につながります。
相続は単なる財産の分配ではなく、家族の絆を再確認する機会でもあります。特別受益について正しく理解し、公平で円満な相続を実現しましょう。
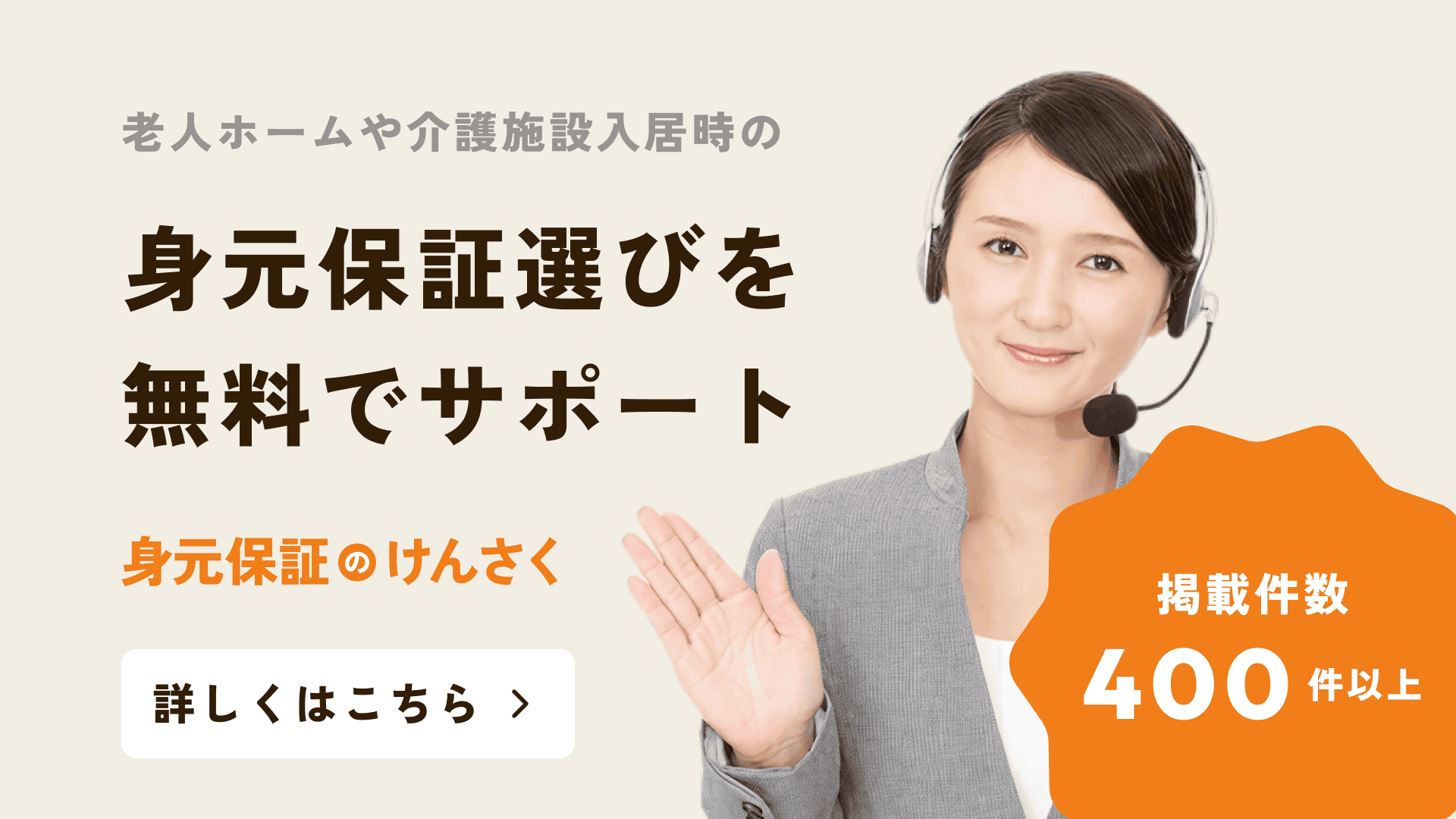
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)