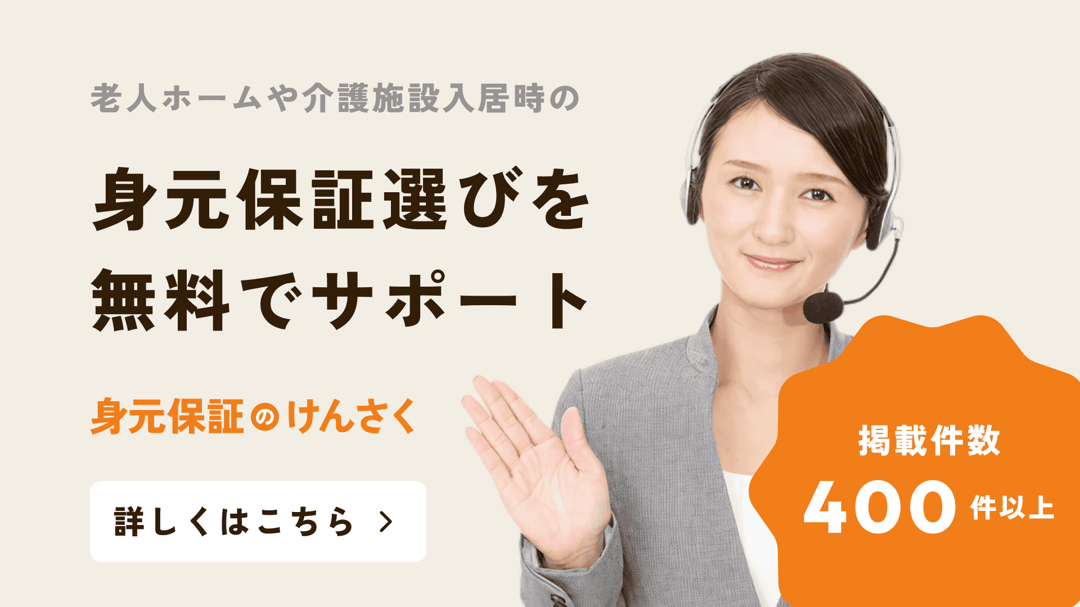.png)
【一覧表で比較】要介護2と要介護3の違いとは?できること・受けられるサービスを徹底解説
更新日: 2025年09月04日
「親が要介護2と認定されたけど、お隣の方は要介護3らしい。一体、何が違うの?」 「認定結果は出たけど、具体的にどんなサービスが、どのくらい使えるのか知りたい」
介護保険の「要介護度」。数字が一つ違うだけで、ご本人の状態や利用できるサービスの内容は大きく変わります。特に「要介護2」と「要介護3」は、在宅生活を続けるか、施設入所を本格的に検討するかの大きな分岐点とも言われています。
この記事では、その重要な違いについて、分かりやすい比較表を用いながら、状態の目安から利用できるサービスまで、どこよりも詳しく解説していきます。
結論:要介護2と3の早わかり比較表
詳しい説明の前に、まずは両者の違いを一覧で見てみましょう。
比較項目 | 要介護2 | 要介護3 |
状態のキーワード | 部分的な介助が必要 | 常時の介助が必要 |
状態の目安 | ・立ち上がりや歩行に支えが必要 | ・立ち上がりや歩行が自力では困難 |
認知機能の目安 | 軽度の認知機能低下が見られることがある | 日常生活に支障が出るレベルの認知機能低下が見られることが多い |
特別養護老人ホーム(特養)への入所 | 原則として対象外 | 原則として入所対象となる |
区分支給限度額の目安 | 約197,000円/月 | 約270,000円/月 |
※区分支給限度額は、介護保険で利用できるサービス費用の上限額です(地域や年度により変動します)。
【部分的な介助が必要】「要介護2」とはどんな状態?
要介護2は、日常生活の基本的な動作は自分でできるものの、立ち上がりや歩行といった複雑な動作に支えが必要な状態です。
状態の目安と「できること・できないこと」の例
- できることの例: 食事や排泄は、見守りや声かけがあれば自分でできることが多い。
- できないこと・支援が必要なことの例:
- 立ち上がり・歩行: 杖や手すりなどの支えがないと不安定。
- 入浴: 浴槽をまたぐ、体を洗うといった動作に一部介助や見守りが必要。
- 家事: 掃除や調理といった複雑な家事を一人で行うのは難しい。
- 金銭管理: 複雑な金銭管理や手続きに支援が必要になることがある。
利用できる主な介護サービス
在宅生活を支えるサービスが中心となります。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- デイサービス(通所介護)
- 訪問看護
- 福祉用具のレンタル(手すり、歩行器など)
【常時の介助が必要】「要介護3」とはどんな状態?
要介護3は、要介護2よりも心身機能が低下し、日常生活の多くの場面で介助が必要な状態です。自力で立ち上がったり歩いたりすることが困難になります。
状態の目安と「できること・できないこと」の例
- できることの例: 簡単な意思表示や、一部の動作は可能。
- できないこと・支援が必要なことの例:
- 立ち上がり・歩行: ほぼ全面的に介助が必要。車椅子の利用が多くなる。
- 食事・排泄・入浴: ほぼ全面的に介助が必要。
- 認知機能: 日常生活に支障をきたすレベルの問題行動や理解力の低下が見られることが多い。
利用できる主な介護サービス
要介護2のサービスに加え、より手厚い支援や施設サービスの利用が本格的な選択肢となります。
- 特別養護老人ホーム(特養)への入所申込み
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- ショートステイ(短期入所生活介護)の利用頻度増加
- 福祉用具のレンタル(車椅子、介護用ベッドなど)
【重要】ここが違う!要介護2と3を分ける3つのポイント
ポイント①:日常生活の自立度の違い
一言でいえば、「部分的な介助」か「ほぼ全面的な介助」かが大きな違いです。要介護2は「支えがあれば何とかできる」場面が多いのに対し、要介護3は「介助がなければ日常生活を送ることが困難」な状態を指します。
ポイント②:認知機能の状態の違い
要介護3では、認知症の症状がより顕著になり、徘徊や妄想、暴力行為といったBPSD(行動・心理症状)への対応がより専門的に求められるケースが増えます。
ポイント③:利用できるサービスの幅(特に特養入所の可否)
これが制度上の最も大きな違いです。特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方が入所対象となります。そのため、要介護3と認定されることは、施設入所という選択肢が本格的に開かれることを意味します。
介護認定の申請・更新の流れについても知っておこう
要介護認定は、市区町村の窓口で申請後、訪問調査と主治医の意見書をもとに専門家が審査し、決定されます。結果に納得できない場合は不服申し立ても可能です。また、認定には有効期間があり、定期的に更新が必要です。状態が大きく変わった場合は、有効期間の途中でも**「区分変更申請」**ができます。
まとめ:違いを理解し、ご本人に最適なケアプランを
要介護2と要介護3の違いを正しく理解することは、ご本人に合った介護サービスを選び、生活の質を維持・向上させるために非常に重要です。
- 要介護2: 在宅サービスを中心に、自立した生活を支える。
- 要介護3: 常時の介助が必要となり、特養への入所も視野に入る。
介護度はあくまで一つの目安です。大切なのは、認定結果を元に、ご本人が今どのような支援を必要としているのかを、ケアマネージャーとしっかり話し合うこと。
今回の記事を参考に、ご本人にとって最適なケアプランを作成するための一歩を踏み出してください。
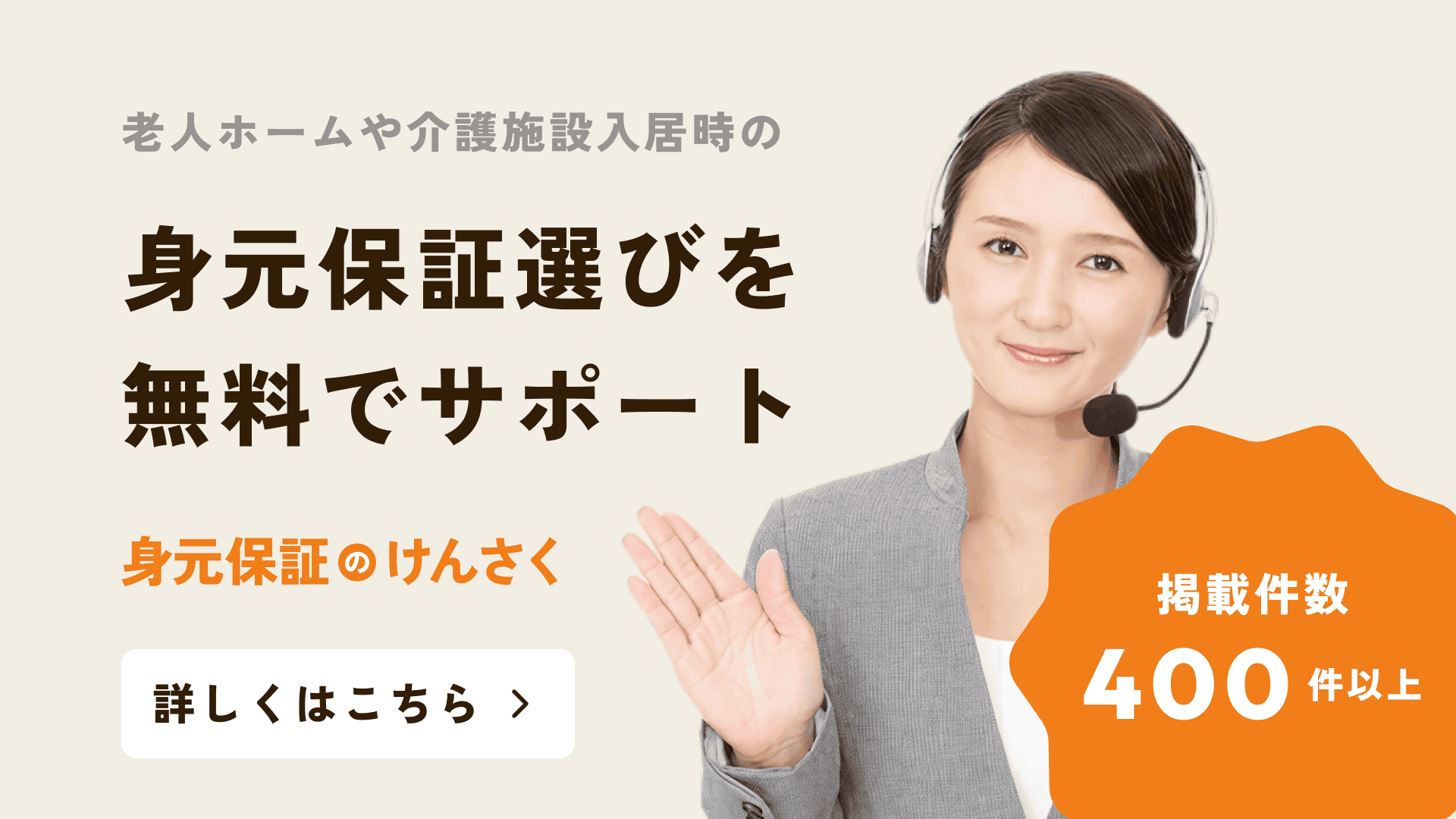
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)