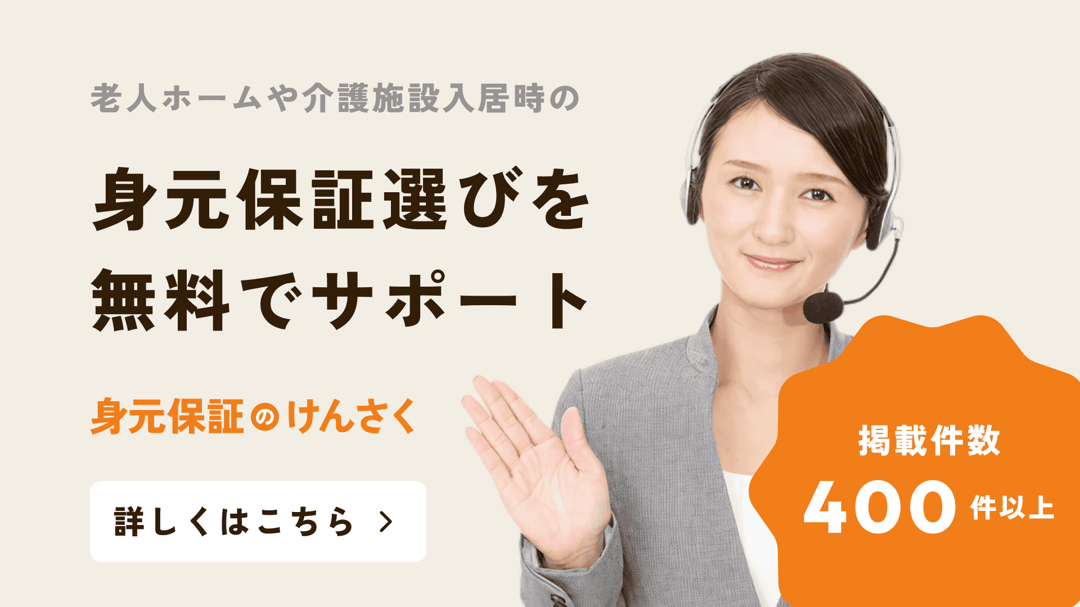.png)
障害厚生年金と老齢厚生年金、どちらが得?【図解】金額・税金・もらい方を徹底比較
更新日: 2025年09月04日
「65歳になり老齢年金の手続きをしたら、『障害年金とどちらかを選べます』と言われたけど、一体どっちがお得なの?」 「障害厚生年金をもらっているけど、このままもらい続けるべきか、老齢年金に切り替えるべきか迷っている…」
障害年金を受給している方が65歳になると直面するのが、この「年金の選択」という非常に重要な問題です。年金の受け取り方は一度選択すると原則変更できないため、慎重な判断が求められます。
この記事では、そんなお悩みを持つ方のために、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらが得かを判断するためのポイントを、「金額」「税金」「将来への影響」といった様々な角度から、図解を交えて分かりやすく徹底比較します。
まずは結論!障害年金と老齢年金の最も重要な違い
詳しい説明の前に、両者の最も大きな違いを一覧表で確認しましょう。ここが選択の基本となります。
比較項目 | 障害年金(障害基礎+障害厚生) | 老齢年金(老齢基礎+老齢厚生) |
計算の基礎 | 障害認定日までの加入記録で計算 | 65歳までの全加入記録で計算 |
税金 | 非課税 | 課税対象(雑所得) |
配偶者加給年金 | なし | あり(条件を満たす場合) |
扶養家族への影響 | 年金は非課税所得のため、税法上の扶養に入りやすい | 年金額によっては扶養から外れる可能性あり |
遺族年金への影響 | 障害年金を受給していた方が亡くなった場合、配偶者への遺族厚生年金の額に影響する場合がある | 老齢年金を受給していた方が亡くなった場合、通常の遺族厚生年金が支給される |
最大のポイントは「税金」です。 障害年金は全額非課税のため、年金の額面が同じでも、手取り額は障害年金の方が多くなります。
【ケース別】65歳になった時の3つの選択肢
障害厚生年金(3級以上)を受給している方が65歳になると、年金の受け取り方は主に以下の3つのパターンから選択することになります。
パターン①:これまで通り「障害年金」を選択
- 受け取る年金: 障害基礎年金 + 障害厚生年金
- メリット: 全額が非課税。
- デメリット: 65歳以降の厚生年金加入期間が年金額に反映されない。配偶者加給年金はつかない。
パターン②:「老齢年金」に切り替えることを選択
- 受け取る年金: 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
- メリット: 65歳までの全加入期間が年金額に反映される。条件を満たせば配偶者加給年金がつく。
- デメリット: 年金が課税対象となる。
パターン③:「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」を組み合わせて選択
- 受け取る年金: 老齢基礎年金 + 障害厚生年金
- メリット: 障害厚生年金分は非課税。老齢基礎年金は満額受け取れる。
- デメリット: 老齢厚生年金は受け取れない。
図解イメージ: ここに、3つの選択肢が分岐するシンプルなイラストや図があると、読者の理解が深まります。
どちらが得?判断するための3つのステップ
では、具体的にご自身がどのパターンを選ぶべきか、判断するためのステップを見ていきましょう。
Step1:ご自身の「年金見込額」を正確に把握する
まず、ご自身の**「障害年金の年金額」と「老齢年金の年金額(見込額)」の両方を正確に知る必要があります。これは、お近くの年金事務所**で相談すれば、「年金見込額試算」をしてもらうことができます。
【相談窓口】 年金の相談は、お近くの年金事務所で行うのが確実です。例えば、山口県防府市にお住まいの方は、山口年金事務所が管轄となりますので、事前に「ねんきんダイヤル」などで予約をしてから相談されることをお勧めします。
Step2:手取り額(可処分所得)でシミュレーションする
年金の額面だけでなく、税金や社会保険料(国民健康保険料、介護保険料)を引いた後の「手取り額」で比較することが非常に重要です。
- 老齢年金を選択した場合: 年金額から所得税・住民税、社会保険料が引かれます。
- 障害年金を選択した場合: 年金は非課税ですが、他の所得があればそれに応じて税金・社会保険料が決まります。
この計算は複雑なため、年金事務所や社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのが最も確実です。
Step3:将来のライフプランを考慮する
目先の手取り額だけでなく、長期的な視点での判断も必要です。
- ご自身の健康状態: 将来、医療費はどのくらいかかりそうか?
- ご家族の状況: 配偶者の扶養に入れるか?万が一の時、配偶者に遺族年金はどのくらい残せるか?
- 働き方: 65歳以降も働く予定はあるか?
まとめ:年金の選択は専門家と相談の上、慎重に
障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらが得かは、お一人おひとりの厚生年金の加入記録、ご家族の状況、そしてライフプランによって全く異なります。
- 一般的に、年金額が同程度なら非課税である「障害年金」が有利なケースが多い。
- しかし、配偶者加給年金の対象になる場合などは「老齢年金」が有利になることも。
- 判断の鍵は、額面ではなく「手取り額」と「将来への影響」で比較すること。
この選択は、あなたのこれからの生活を左右する非常に重要な決断です。ご自身だけで判断せず、必ず年金事務所や社会保険労務士といった専門家に相談し、最もご自身にとって有利な方法を選択してください。
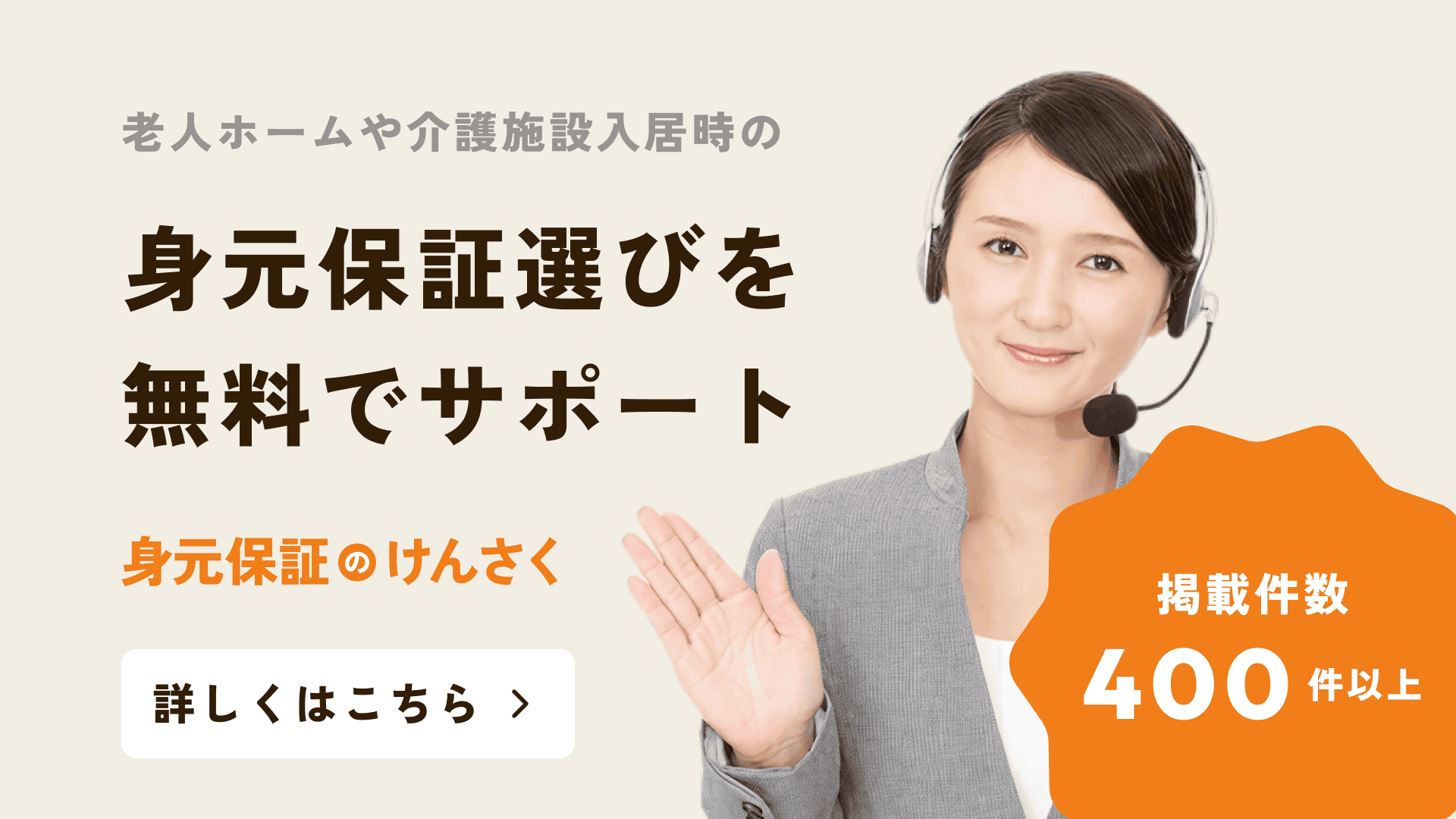
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)