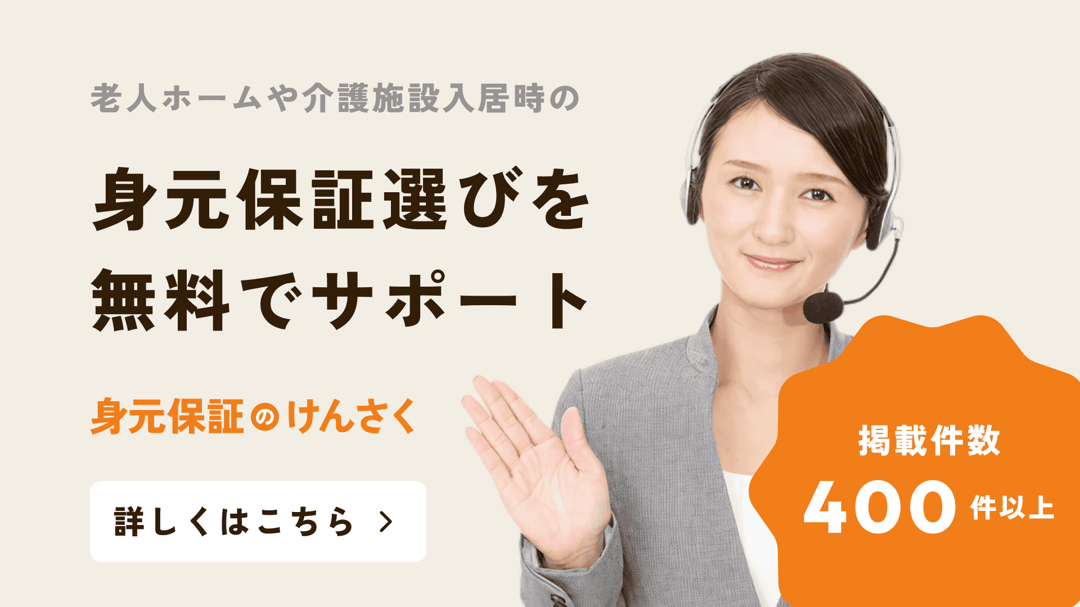.png)
年金の手取りが「額面」より少ないのはなぜ?引かれる税金・保険料の種類と、手取りを増やす方法を徹底解説
更新日: 2025年09月04日
初めて年金を受け取った時、「あれ?通知された金額(額面)より、実際に振り込まれた金額(手取り)が少ない…」と驚いた方はいませんか?
会社員時代の給与と同じように、年金も支給額の全額がそのまま手元に入るわけではありません。 年金からは、私たちが社会で暮らしていくために必要な「税金」と「社会保険料」が天引き(特別徴収)されています。
この記事では、あなたの年金から「何が、いくら引かれているのか」、そして「手取り額を少しでも増やすための賢い方法」について、専門用語をかみ砕いて分かりやすく解説します。
【図解】年金の手取り額はこう決まる!
まず、年金の「額面」と「手取り」の関係をイメージで掴みましょう。
年金の総支給額(額面)
- ① 税金(所得税・住民税)
- ② 社会保険料(介護保険料・健康保険料)
= 実際に振り込まれる金額(手取り額)
では、それぞれの中身を詳しく見ていきましょう。
引かれるもの①:税金(所得税・住民税)
年金は、税法上「雑所得」として扱われ、課税の対象となります。
1. 所得税
年金の収入金額から**「公的年金等控除」**という、年金受給者のための特別な経費のようなものを差し引いた金額に対してかかります。さらに、そこから基礎控除や配偶者控除、扶養控除なども引かれるため、実際に課税される金額は額面よりかなり少なくなります。
- ポイント: 年金収入が一定額以下で、他に所得がなければ確定申告は不要な場合が多いです。
2. 住民税
前年の所得を元に計算される、お住まいの都道府県・市区町村に納める税金です。計算方法は所得税と似ていますが、控除額などが異なります。
引かれるもの②:社会保険料
私たちが医療や介護サービスを受けるために必要な保険料も、年金から天引きされます。
1. 介護保険料
65歳以上の方全員が対象となります。保険料は、お住まいの市区町村や前年の所得によって決まります。
2. 国民健康保険料 / 後期高齢者医療保険料
- 65歳〜74歳の方: 国民健康保険に加入している場合、その保険料(国民健康保険税)が天引きされることがあります。
- 75歳以上の方: 全員が**「後期高齢者医療制度」**に加入し、その保険料が天引きされます。
3ステップでわかる!あなたの年金手取り額・計算シミュレーション
ご自身の正確な手取り額を知るには、以下のステップで計算します。
ステップ1:ご自身の年金「総支給額(額面)」を確認する
毎年誕生月に日本年金機構から送られてくる**「ねんきん定期便」や、年金の受給開始時に届く「年金証書」**で年間の総支給額を確認します。
ステップ2:引かれる「税金」と「社会保険料」の金額を確認する
- 税金額: 毎年6月頃に市区町村から送付される**「住民税決定通知書」**で確認できます。
- 社会保険料額: 毎年7月頃に市区町村から送付される**「介護保険料決定通知書」「後期高齢者医療保険料決定通知書」**などで確認できます。
ステップ3:「総支給額」から「税金+社会保険料」を差し引く
ステップ1の金額から、ステップ2で確認した税金と社会保険料の合計額を引いたものが、年間の手取り額の目安になります。
【実践編】年金の手取り額を増やす!3つの賢い方法
天引きされる金額は決まっていますが、合法的な工夫で手取り額を増やす(=税金や保険料を安くする)ことが可能です。
節約術①:各種「所得控除」をフル活用する
税金を計算する元となる「所得」を減らすのが、節税の基本です。
- 生命保険料控除、地震保険料控除: 支払っている保険料があれば、年末調整や確定申告で申告しましょう。
- 医療費控除: 年間の医療費がたくさんかかった場合、申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金): 掛け金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果があります。
節約術②:「確定申告」で払いすぎた税金を取り戻す
年金からの所得税は、概算で天引き(源泉徴収)されています。上記のような各種控除を適用するために確定申告をすることで、払いすぎていた税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。 税金の詳しい相談は、お住まいの地域を管轄する税務署が窓口です。 例えば、山口県防府市にお住まいの方は、山口税務署が管轄となります。
節約術③:専門家に相談する
「控除のことがよくわからない」「確定申告が難しそう」と感じたら、税理士などの専門家に相談するのも一つの手です。費用はかかりますが、それ以上の節税効果が得られる場合もあります。
まとめ:制度を理解し、賢く年金と付き合おう
年金から税金や社会保険料が引かれるのは、私たちが安心して暮らすための社会保障制度を維持するために必要な仕組みです。
- 年金からは「所得税」「住民税」「介護保険料」「健康保険料」が引かれる。
- 手取り額は「ねんきん定期便」や市区町村からの通知書で計算できる。
- 「所得控除」や「確定申告」をうまく活用すれば、手取り額を増やせる可能性がある。
まずはご自身の年金から何が引かれているのかを正しく把握することから始めましょう。制度を理解し、賢く付き合っていくことが、ゆとりあるセカンドライフにつながります。
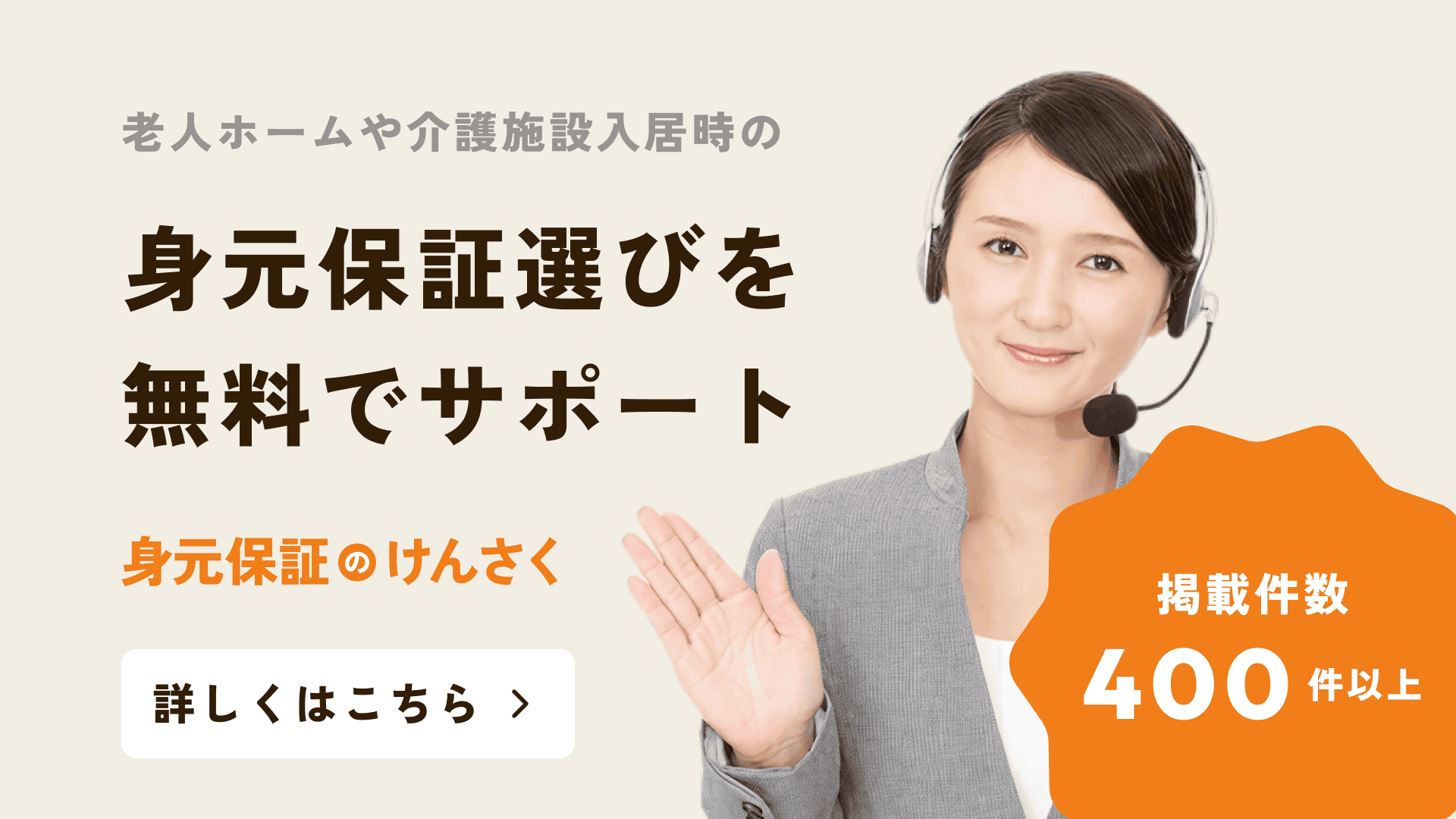
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)