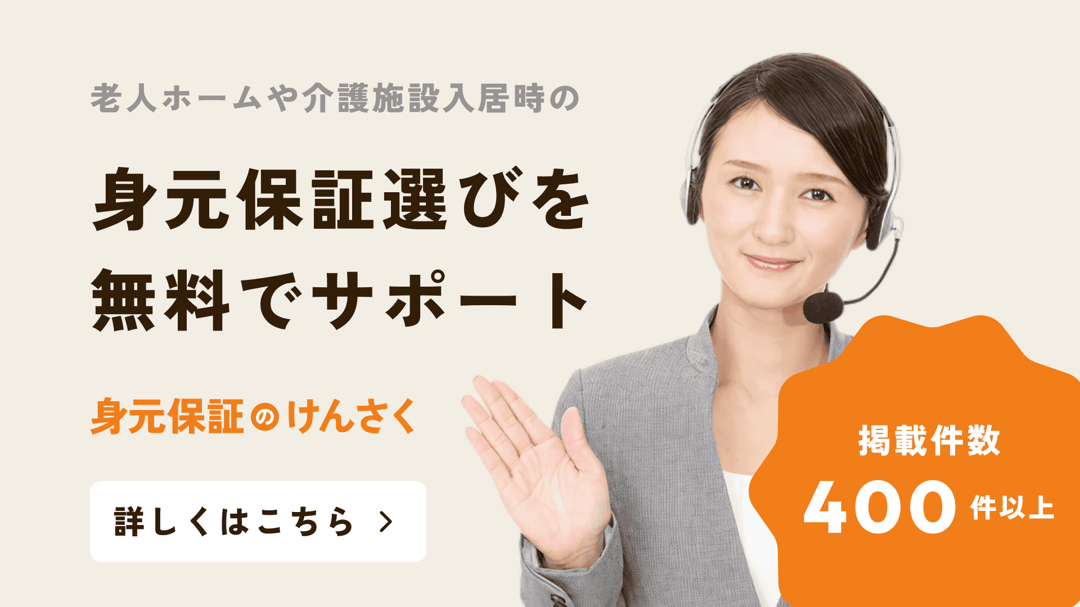.png)
相続の基本から応用まで:知っておきたい相続税の計算方法
更新日: 2025年09月10日
相続は人生の大切な節目ですが、手続きや税金に関する知識がないと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。この記事では、相続における基本的な手続きから、具体的な相続税の計算方法までを分かりやすく解説し、相続トラブルを未然に防ぐための土台を作ります。
1. 相続の基本を理解する
相続とは、故人の財産や権利義務を法定相続人が引き継ぐことです。財産には、土地、建物、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
- 相続財産の種類:
- 動産・不動産: 土地や建物、自動車など。
- 金融資産: 預貯金、株式、債券など。
- 法定相続人: 民法で定められた相続人の順位と割合です。第一順位は子供、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹。配偶者は常に相続人となります。
2. 相続手続きの流れ
相続は法律に基づいた手続きが必要で、これを怠るとトラブルにつながることがあります。
- 死亡届の提出: 故人が亡くなった日から7日以内に市区町村役場に提出します。
- 遺言書の確認: 故人が遺言書を残しているか確認し、あれば家庭裁判所で検認手続きを行います。
- 相続人の確定: 戸籍謄本などを用いて、法定相続人を特定します。
- 遺産分割協議: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
- 相続税の申告・納付: 遺産総額が基礎控除額を超える場合、申告と納付が必要です。
3. 相続税の計算方法
相続税は、遺産の総額が一定額を超える場合に課税されます。
1. 基礎控除額の計算
相続税がかかるかどうかの基準となるのが基礎控除額です。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
2. 相続税の税率
相続税は、累進課税制度を採用しており、課税遺産総額に応じて税率が10%から55%まで適用されます。高額の遺産ほど税率が高くなる仕組みです。
3. 納税までの手順
- 遺産総額の計算: 不動産、預貯金、株式などを評価し、総額を算出します。
- 課税遺産総額の計算: 遺産総額から基礎控除額を差し引きます。
- 相続税額の計算: 各相続人の課税対象額に税率を適用し、相続税額を算出します。
- 申告・納付: 相続開始日から10ヶ月以内に税務署に申告し、納付します。
4. 知っておきたい相続税対策
相続税対策は、生前から計画的に行うことが重要です。
- 生前贈与: 毎年110万円までの贈与は非課税です。この制度を長期的に活用することで、相続時の遺産総額を減らすことができます。
- 生命保険の活用: 生命保険金は一定額まで非課税で受け取ることができ、納税資金としても利用できます。
- 不動産の活用: 不動産は現金に比べて評価額が低くなることが多く、相続税対策として有効です。
まとめ
相続は、家族にとって大切な財産を次の世代に引き継ぐ重要なプロセスです。
相続トラブルを未然に防ぐためには、相続の基本知識を身につけ、相続税の計算方法を理解し、早めの対策を講じることが不可欠です。
相続手続きや税務は複雑なため、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。事前の準備と計画的な行動が、円満な相続を実現する鍵となります。
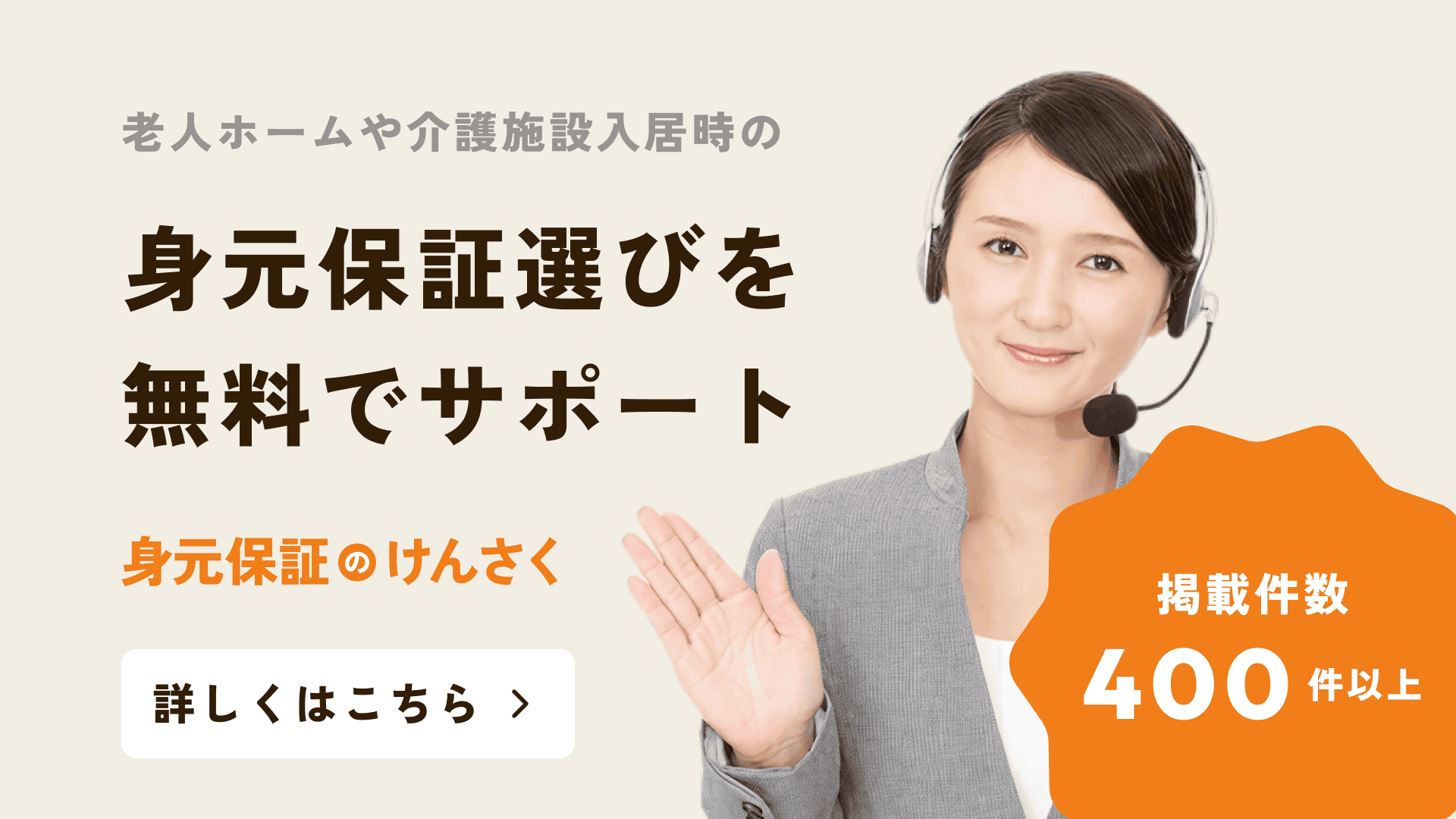
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)