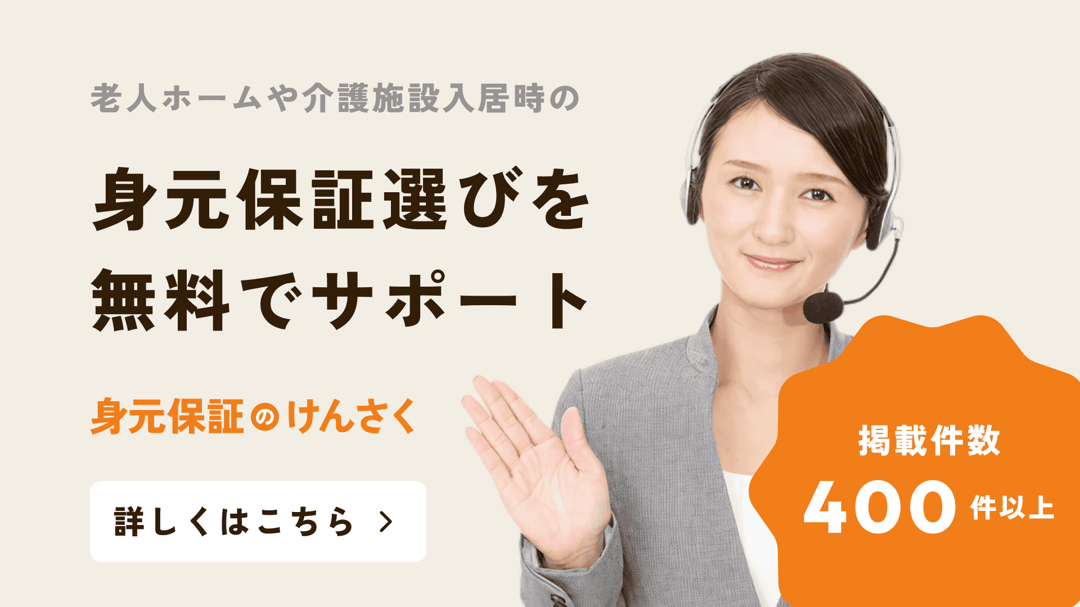.png)
相続した遺産に確定申告は必要?相続税と所得税の関係を徹底解説
更新日: 2025年09月10日
相続が発生すると、遺産に関する税金の手続きが必要になります。多くの人が混乱するのが、**「相続税」と「所得税」**の関係です。この記事では、相続した遺産に対する確定申告が必要かどうかを詳しく解説し、2つの税金の違いと手続きについて説明します。
相続税と所得税、それぞれの意味
1. 相続税
相続税は、亡くなった人から財産を引き継ぐ際に、その遺産そのものに課される税金です。
- 課税対象: 遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合にのみ、その超えた部分に課税されます。
- 申告・納税期限: 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。
2. 所得税
所得税は、個人が1年間に得た収入に対して課される税金です。相続によって受け取った遺産自体に所得税はかかりません。
- 課税対象: 給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得など、収入を生んだ場合に課税されます。
- 申告・納税期限: 通常、翌年の3月15日までです。
相続と確定申告の関係
相続税を支払ったからといって、確定申告が不要になるわけではありません。 以下のケースでは、相続後に別途、所得税の確定申告が必要になります。
1. 「準確定申告」
故人が亡くなった年に得た所得に対する確定申告です。故人が自営業者や不動産所得などがあった場合、相続人が故人に代わって申告を行う必要があります。相続の開始(亡くなった日)から4ヶ月以内が期限です。
2. 遺産から収入を得た場合
相続した遺産そのものには所得税はかかりませんが、遺産が将来的に収入を生んだ場合、その収入は所得税の課税対象となります。
- 例1: 相続した不動産を売却した 売却して利益が出た場合、**「譲渡所得税」**として所得税が課されます。
- 例2: 相続した不動産を賃貸している 得られた賃料収入は**「不動産所得」**として、毎年確定申告が必要です。
- 例3: 相続した株式から配当金を得た 得られた配当金は**「配当所得」**として確定申告が必要です。
手続きをスムーズに進めるためのポイント
- 税金の関係を正しく理解する: 相続税と所得税は別の税金であり、それぞれの手続きが必要です。
- 必要書類を準備する: 源泉徴収票や収入に関する証明書など、確定申告に必要な書類を事前に確認し、漏れなく揃えましょう。
- 専門家に相談する: 複雑な相続や多額の遺産がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
相続した遺産には、「相続税」と「所得税」という2つの税金が関連してきます。
相続税は遺産自体に課され、所得税は遺産から生じる収入に課されるという違いを理解しておくことが重要です。
相続が発生した際は、相続税の申告だけでなく、故人の所得に対する準確定申告や、遺産から得た収入に対する確定申告も必要になる可能性があることを覚えておきましょう。これらの手続きを適切に行うことが、税務上のリスクを避け、安心して遺産を管理するための第一歩となります。
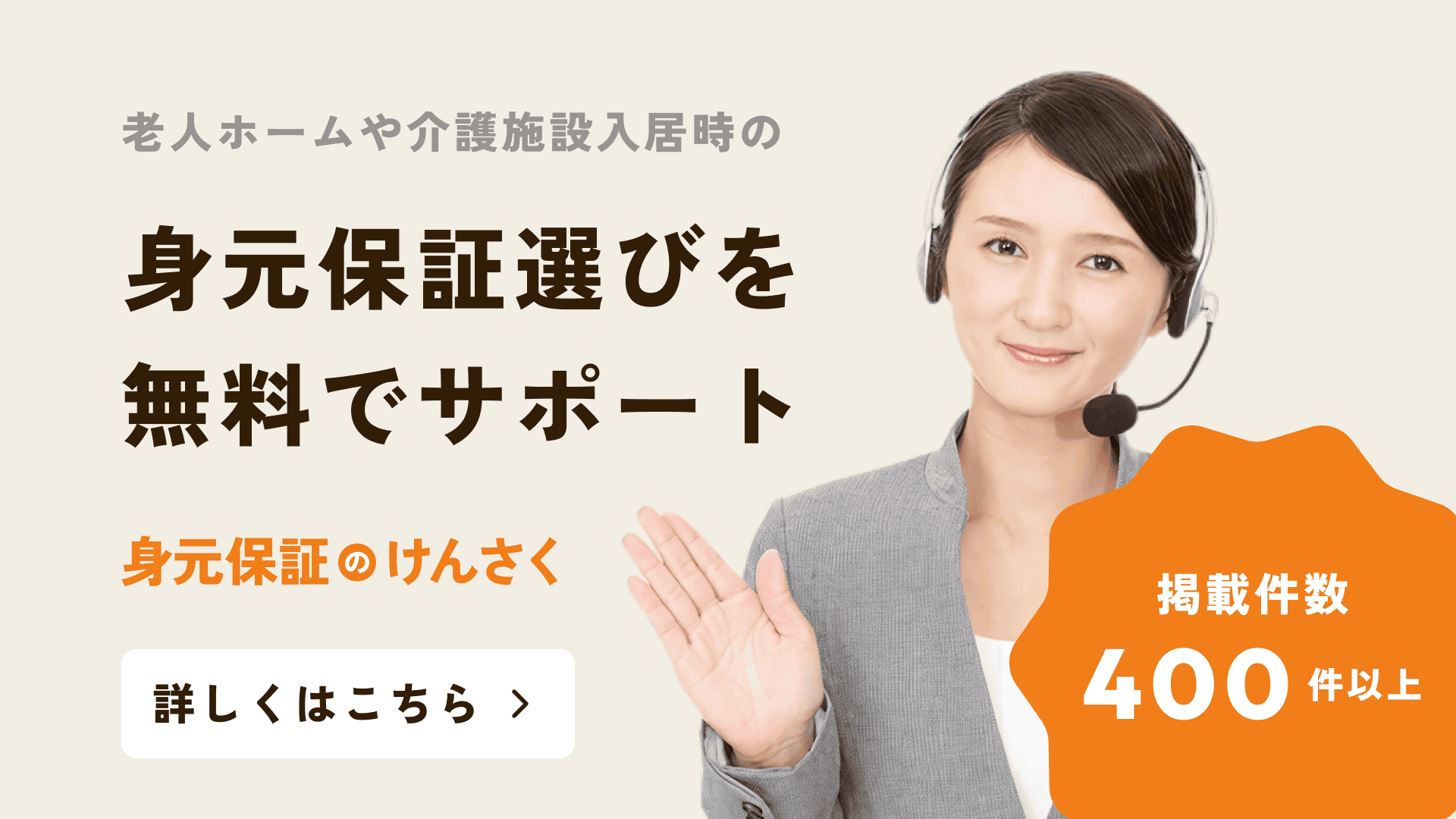
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)