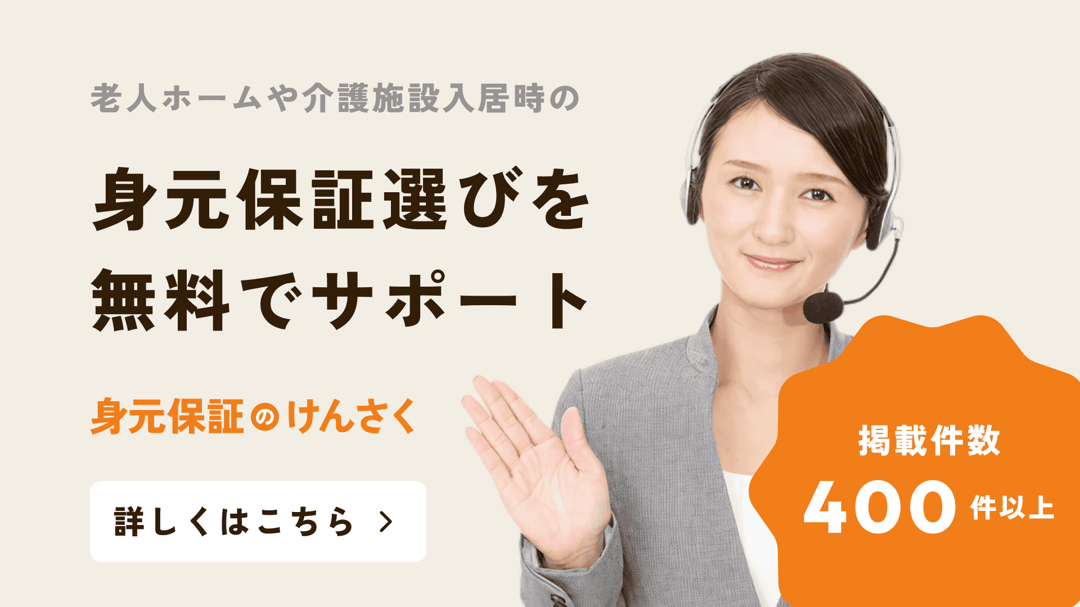.png)
相続放棄の期限は3ヶ月!知っておくべき「熟慮期間」
更新日: 2025年09月10日
相続に関する手続きは複雑ですが、特に相続放棄を考えている方は、**「熟慮期間」**と呼ばれる3ヶ月の期限を理解しておくことが非常に重要です。この期間を過ぎると相続放棄ができなくなるため、正しい知識を持って行動することが大切です。
熟慮期間とは?
熟慮期間とは、相続が開始したことを知った日から3ヶ月間のことを指します。この期間内に、相続人は遺産を相続するか、それとも放棄するかを決定しなければなりません。
- なぜ3ヶ月なの?: 相続にはプラスの財産(資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。この期間は、遺産の内容を正確に調査し、相続するかどうかを慎重に考えるための時間として設けられています。
- 期限を過ぎると?: もし熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなければ、法律上、自動的に相続を承認したとみなされます。 その結果、負債もすべて引き継ぐことになり、多額の借金を背負うリスクがあります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄を決定した場合、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行う必要があります。
- 必要書類の準備:
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本(被相続人との関係を証明するもの)
- 住民票の写し(申述人の居住地を確認するもの)
- 家庭裁判所への申述: 必要書類を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
- 裁判所の審査と通知: 提出された書類を基に審査が行われ、問題がなければ相続放棄が認められた旨の通知が届き、手続きが完了します。
熟慮期間を過ぎてしまったら?
やむを得ない事情で3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合でも、裁判所に申し立てることで熟慮期間の延長が認められる可能性があります。
- 延長が認められるケースの例:
- 遺産の内容が複雑で把握に時間がかかる。
- 相続人が遠方に住んでいて手続きが困難。
- 体調不良など、健康上の理由で手続きができない。
延長が認められるかどうかはケースバイケースなので、専門家に相談して適切な対応を取りましょう。
相続に関する時効
相続には、相続放棄の期限とは別に、以下のような時効も存在します。
- 相続権の時効: 相続開始後10年が経過すると、相続権が消滅し、遺産を請求することができなくなります。
- 相続税の時効: 相続税の申告・納付義務は、相続開始後5年(故意に申告しなかった場合は7年)で時効となります。しかし、意図的に納税を避けると、後から追徴課税や罰則が科されることがあるため、適切に申告することが重要です。
まとめ
相続放棄は、負債を回避するための有効な手段ですが、「熟慮期間」という3ヶ月の期限を厳守する必要があります。
- 相続が発生したら、まずは遺産(プラスとマイナス両方)を速やかに調査しましょう。
- 判断に迷ったり、期限が迫っていたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが最も賢明な選択です。
正しい知識と早めの行動が、後悔のない相続を実現する鍵となります。
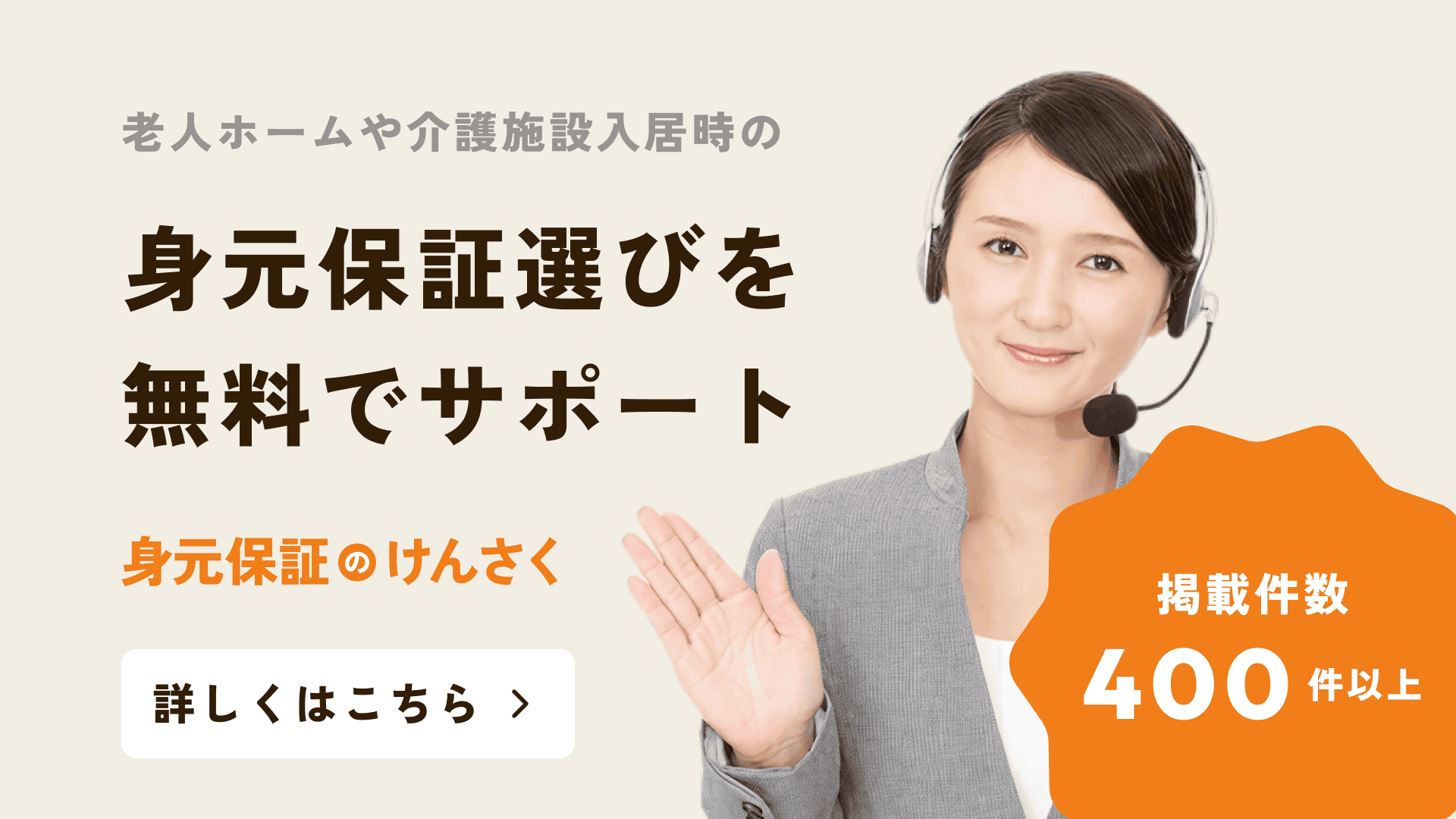
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)