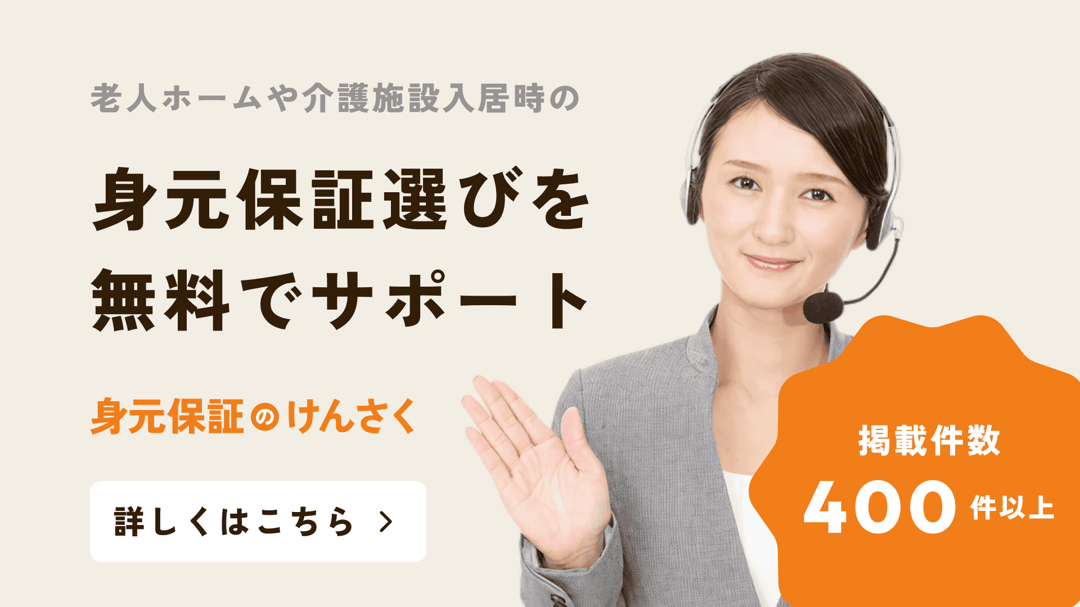.png)
むせる・飲み込みにくい方へ。誤嚥性肺炎を予防する食事の全知識【チェックリスト付】
更新日: 2025年09月04日
「最近、食事中にむせることが増えた…」 「親の飲み込む力が弱ってきて、肺炎が心配…」
加齢とともに増える「むせ」や「飲み込みにくさ」。それは、高齢者の命に関わることもある**「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」**のサインかもしれません。
しかし、ご安心ください。誤嚥性肺炎は、日々の食事の工夫によって、そのリスクを大きく減らすことが可能です。
この記事では、誤嚥性肺炎の基本から、今日からすぐに実践できる具体的な食事のポイント、そして食事以外の予防策まで、網羅的に解説します。大切なご自身やご家族の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
まずはセルフチェック!食事でできる誤嚥予防10のポイント
現在の食事習慣が安全かどうか、まずはチェックしてみましょう。
- [ ] 体をしっかり起こし、良い姿勢で食事をしている
- [ ] 足が床にしっかり着く椅子に座っている
- [ ] 食事中はテレビを消し、会話も控えめにしている
- [ ] 焦らず、ゆっくり時間をかけて食べている
- [ ] 食べ物は、飲み込みやすい柔らかさ・大きさにしている
- [ ] 水やお茶を飲むときは、むせずに飲めている(必要ならとろみ剤を使用)
- [ ] 一度に口に入れる量は、ティースプーン1杯程度にしている
- [ ] 食事の前に、口や舌の準備体操をしている
- [ ] 食後すぐに横にならず、しばらく座った姿勢を保っている
- [ ] 食後は必ず歯磨きやうがい(口腔ケア)をしている
3つ以上チェックが付かなかった方は、特に注意が必要です。具体的な対策を一緒に見ていきましょう。
そもそも誤嚥性肺炎とは?原因と症状を知ろう
誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、唾液などが、誤って気管に入り込んでしまうこと(=誤嚥)が原因で起こる肺炎です。
なぜ「誤嚥」は起こるのか?
加齢による**「飲み込む力(嚥下機能)」の低下**が主な原因です。他にも、脳梗塞の後遺症、薬の副作用、食事の姿勢が悪いことなどもリスクを高めます。
こんな症状は要注意!
食事中のむせや咳だけでなく、発熱、痰(たん)が増える、声がガラガラする、なんとなく元気がないといった症状もサインかもしれません。気になる症状があれば、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
【実践編】今日からできる!誤嚥を防ぐ食事の9つの工夫
誤嚥を防ぐポイントは「環境」「食べ方」「食べ物」の3つに分けられます。
《環境と姿勢を整える》
1. 正しい姿勢で座る
体をまっすぐ起こし、椅子に深く腰掛けます。足の裏全体が床に着くように高さを調整し、少し前かがみで、顎を軽く引くのが理想的な姿勢です。ベッドで食べる場合も、上半身を90度近くまで起こしましょう。
2. 静かな環境で集中する
食事中はテレビを消し、会話は最小限に。食べることだけに集中できる環境を作りましょう。
3. 食事の時間を十分に確保する
焦りは誤嚥の最大の敵です。「ゆっくり、一口ずつ」を意識できるよう、食事の時間は最低でも30分は確保しましょう。
《食べ方を工夫する》
4. 一口の量を少なくする
一度に口に入れる量は、ティースプーン1杯程度が目安です。口の中のものを完全に飲み込んでから、次の一口を運びましょう。
5. 口腔体操で準備運動
食事の前に、口を大きく開けたり閉じたり、舌を前後左右に動かしたりする「口腔体操」を行うと、口周りの筋肉が目覚め、飲み込みがスムーズになります。
6. 水分は「とろみ」をつけて
水やお茶、汁物などのサラサラした液体は、最も誤嚥しやすいものの一つです。市販のとろみ調整食品を活用し、少しとろみをつけるだけで、格段に飲み込みやすくなります。
《食べ物を選ぶ・調理を工夫する》
7. 飲み込みやすい形状・硬さにする
パサパサしたもの(パン、クッキーなど)、硬いもの(せんべい、根菜など)、サラサラしたものは避けましょう。
- 調理法:「煮る」「蒸す」「茹でる」などで柔らかくする。
- 形状:細かく刻んだり、ミキサーにかけたり、片栗粉やゼラチンでまとめたりする。
8. 栄養バランスを考える
飲み込みやすさだけを考えると、栄養が偏りがちです。肉や魚、卵、豆腐などのタンパク質を、ペースト状にするなど調理法を工夫してしっかり摂り、飲み込む力を支える体力を維持しましょう。
9. 食後の口腔ケアを忘れずに
食後すぐに横になると、胃から食べ物が逆流し、誤嚥の原因になります。食後2時間程度は座った姿勢を保ちましょう。 また、口の中に残った食べカスが細菌の温床にならないよう、食後の歯磨きやうがい(口腔ケア)は徹底しましょう。
【レシピのヒント】こんな食事がおすすめ!飲み込みやすいメニュー例
- 主食: お粥、柔らかく炊いたご飯、パン粥
- 主菜: 鶏ひき肉のあんかけ、白身魚のクリーム煮、茶碗蒸し、豆腐ハンバーグ
- 副菜: 野菜のポタージュ、かぼちゃの煮物(マッシュ状に)、ほうれん草のおひたし(細かく刻む)
- デザート: フルーツゼリー、ヨーグルト、プリン
食事以外も大切!日常生活でできる3つの予防策
- 丁寧な口腔ケア: 虫歯や歯周病菌が誤嚥性肺炎のリスクを高めます。毎食後の歯磨きや、定期的な歯科受診を心がけましょう。
- 適度な運動: ウォーキングなどの軽い運動は、全身の筋力だけでなく、飲み込みに関わる筋肉の維持にもつながります。
- 禁煙・節酒: 喫煙や過度な飲酒は、喉の反射機能を低下させ、誤嚥のリスクを高めます。
まとめ:毎日の食事を見直して、誤嚥性肺炎をしっかり予防しよう
誤嚥性肺炎は、日々の小さな工夫の積み重ねで予防できる病気です。 今回ご紹介したポイントの中から、できそうなことを一つでも良いので、今日から始めてみませんか? 毎日の食事が、恐怖の時間ではなく、安全で楽しい時間であり続けるために。この記事が、あなたと大切なご家族の健康を守る一助となれば幸いです。
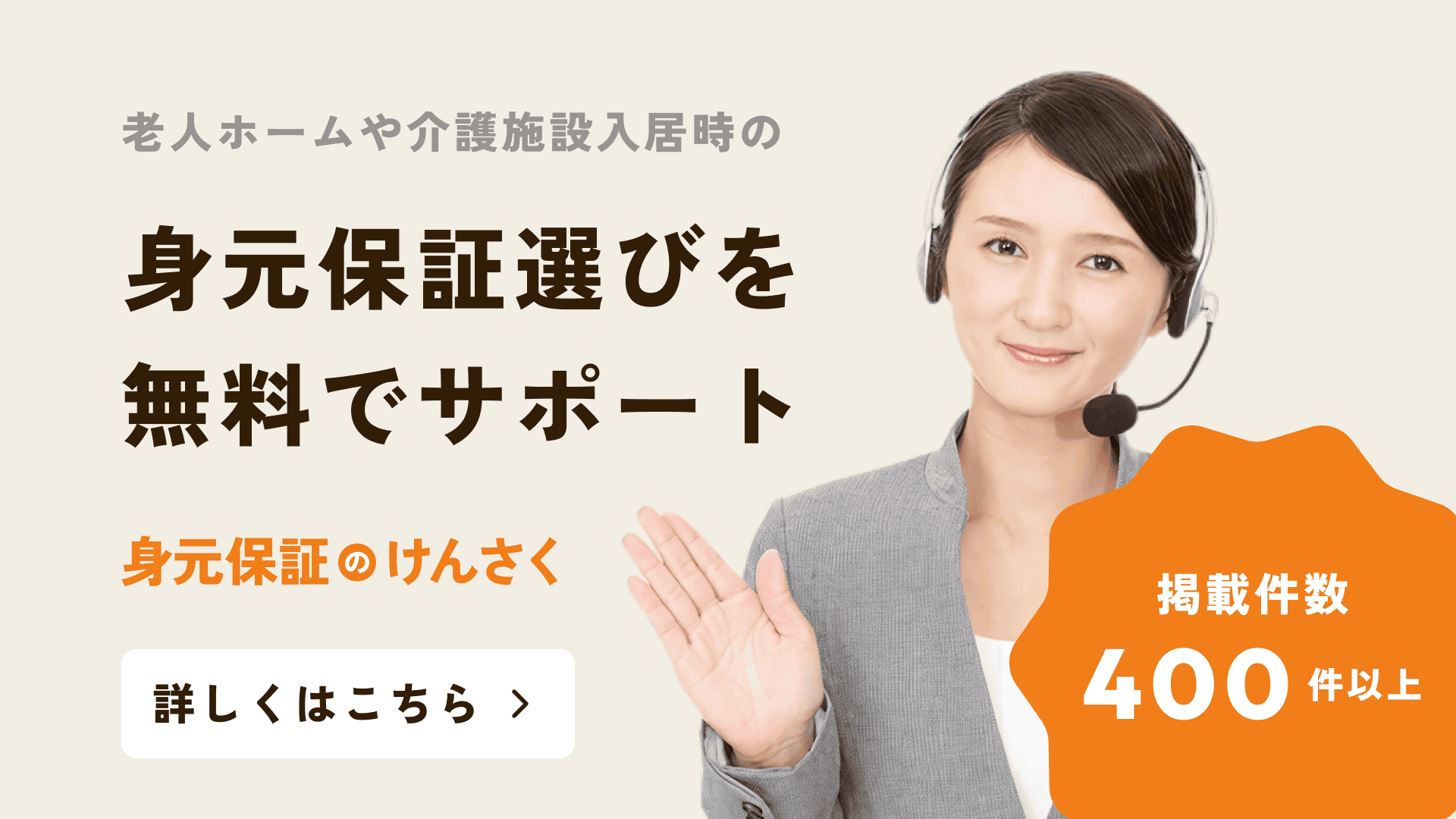
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)