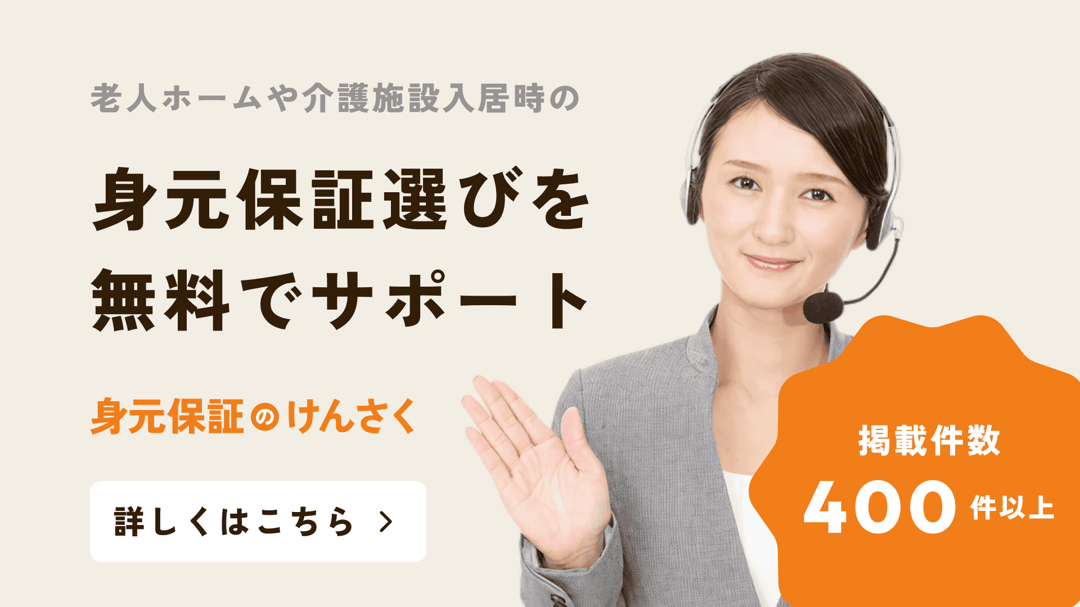.png)
アルツハイマー型認知症と診断されたら寿命は?平均余命と穏やかに過ごすために家族ができること
更新日: 2025年09月04日
「アルツハイマー型認知症と診断されたとき、ご家族が最も気になることの一つが『あと、どのくらい一緒にいられるのだろうか』という寿命の問題ではないでしょうか。
この問いに対する不安は、計り知れないほど大きいものだと思います。この記事では、アルツハイマー型認知症と寿命の関係について、現在わかっている医学的な情報と、残された時間を少しでも穏やかで豊かなものにするために、ご家族ができることを丁寧にお伝えします。
いたずらに不安を煽るのではなく、正しい知識を持つことで、これからの時間をどう大切に過ごしていくかを考える一助となれば幸いです。
アルツハイマー型認知症と診断された後の平均余命
まず、最も気になる平均的な余命についてです。
一般的に、アルツハイマー型認知症と診断されてからの平均余命は8年〜10年ほどと言われています。しかし、これはあくまで平均的なデータであり、個人差が非常に大きいのが実情です。
- 発症年齢: 若い年齢で発症する「若年性アルツハイマー」の場合、進行が比較的緩やかで、診断後の期間が長くなる傾向があります。
- 健康状態: もともとの持病の有無や体力によって、経過は大きく異なります。
- ケアの質: 診断後、どのような医療や介護を受けるかによって、生活の質も寿命も変わってきます。
大切なのは、数字に一喜一憂するのではなく、ご本人の状態を正しく理解し、一日一日を大切に過ごすための環境を整えることです。
なぜ寿命に影響するのか?認知症の進行と末期症状
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞がゆっくりと壊れていく病気です。病気そのものが直接の死因となることは稀で、多くは進行に伴う身体機能の低下が寿命に影響します。
初期〜中期:記憶障害から日常生活への支障へ
はじめは物忘れから始まり、徐々に時間や場所が分からなくなったり、簡単な計算や判断ができなくなったりします。この段階では、日常生活に支障は出始めますが、身体的には元気なことが多いです。
末期:身体機能の低下と合併症のリスク
進行すると、脳からの指令が全身にうまく伝わらなくなり、様々な身体機能が低下します。
- 歩行障害: 歩くことが困難になり、寝たきりの状態になる。
- 嚥下(えんげ)障害: 食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなる。
- 免疫力の低下: 全身の体力が落ち、感染症にかかりやすくなる。
特に、**嚥下障害による「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」**は、食べ物や唾液が誤って気管に入り込むことで起こる肺炎で、末期の認知症の方にとって最も注意すべき合併症の一つです。こうした合併症が、最終的に寿命を左右する大きな要因となります。
穏やかな時間を延ばすために、家族ができる3つのこと
「寿命を延ばす」という表現は適切ではないかもしれません。しかし、ご本人がその人らしく、少しでも長く穏やかな時間を過ごせるように、ご家族ができることはたくさんあります。
① 早期からの適切な医療・介護の導入
診断を受けたら、できるだけ早く専門的なサポートを開始することが重要です。
- 早期診断・治療: 認知症の進行を緩やかにする薬の服用や、BPSD(行動・心理症状)を抑えるための治療を早期に始める。
- 介護保険サービスの活用: ケアマネージャーに相談し、デイサービスや訪問介護などを利用して、ご本人の心身機能の維持と、ご家族の負担軽減を図る。
② 生活習慣の見直しで進行を緩やかに
健康的な生活習慣は、脳の健康を保ち、認知症の進行を遅らせる可能性があると言われています。
- バランスの良い食事: 特に魚や野菜、果物を中心とした食生活を心がける。
- 定期的な運動: 無理のない範囲での散歩や体操は、脳の血流を良くし、体力の維持につながります。
- 知的活動の継続: 趣味や人との交流、簡単な計算ドリルなど、脳を使い続けることが大切です。
③ 安心できる環境と精神的なサポート
ご本人が混乱や不安を感じず、安心して過ごせる環境は、心の安定に不可欠です。
- 穏やかなコミュニケーション: 否定したり、間違いを正したりせず、ご本人の言葉に耳を傾け、気持ちに寄り添う。
- 安全な住環境: 転倒防止のための手すりの設置や、危険物の撤去など、安全に過ごせる家づくりを。
- 家族自身のケア: 介護するご家族が心身ともに健康であることが、結果的にご本人の安心につながります。一人で抱え込まず、ショートステイなどを利用して休息をとることも重要です。
最期のときを穏やかに迎えるための終末期ケア(ターミナルケア)
認知症が末期に至ったとき、治療の目的は病気の根治から**「いかに苦痛なく、穏やかに過ごせるか」**という緩和ケアへと移行します。
- 疼痛管理: 痛みを適切に取り除き、穏やかな表情で過ごせるようにする。
- 栄養と水分の補給: 食べられなくなった場合でも、脱水などを防ぎ、苦痛を和らげるためのケアを行う。
- 尊厳を守るケア: 清潔を保ち、心地よい環境を整え、最期まで一人の人間として尊厳が守られるよう努める。
まとめ:寿命の長さだけでなく「人生の質」を大切に
アルツハイマー型認知症と寿命の関係は、一概に「何年」と言えるものではありません。しかし、確かなことは、診断後の関わり方次第で、残された時間の質は大きく変わるということです。
- 平均余命はあくまで目安。個人差が大きいことを理解する。
- 寿命に影響するのは、進行に伴う身体機能の低下と合併症。
- 早期からの医療・介護、生活習慣の見直し、安心できる環境づくりが鍵。
寿命の長さだけに目を向けるのではなく、ご本人がその人らしく、少しでも笑顔で穏やかに過ごせる時間(QOL:クオリティ・オブ・ライフ)をいかに創り出していくか。その視点を持つことが、ご家族にとっても、ご本人にとっても、かけがえのない時間を過ごすための最も大切な心構えなのかもしれません。
もし、あなたが一人で悩んでいるなら、まずは地域包括支援センターやかかりつけ医に相談してみてください。きっと、あなたとご家族を支える道筋が見つかるはずです。
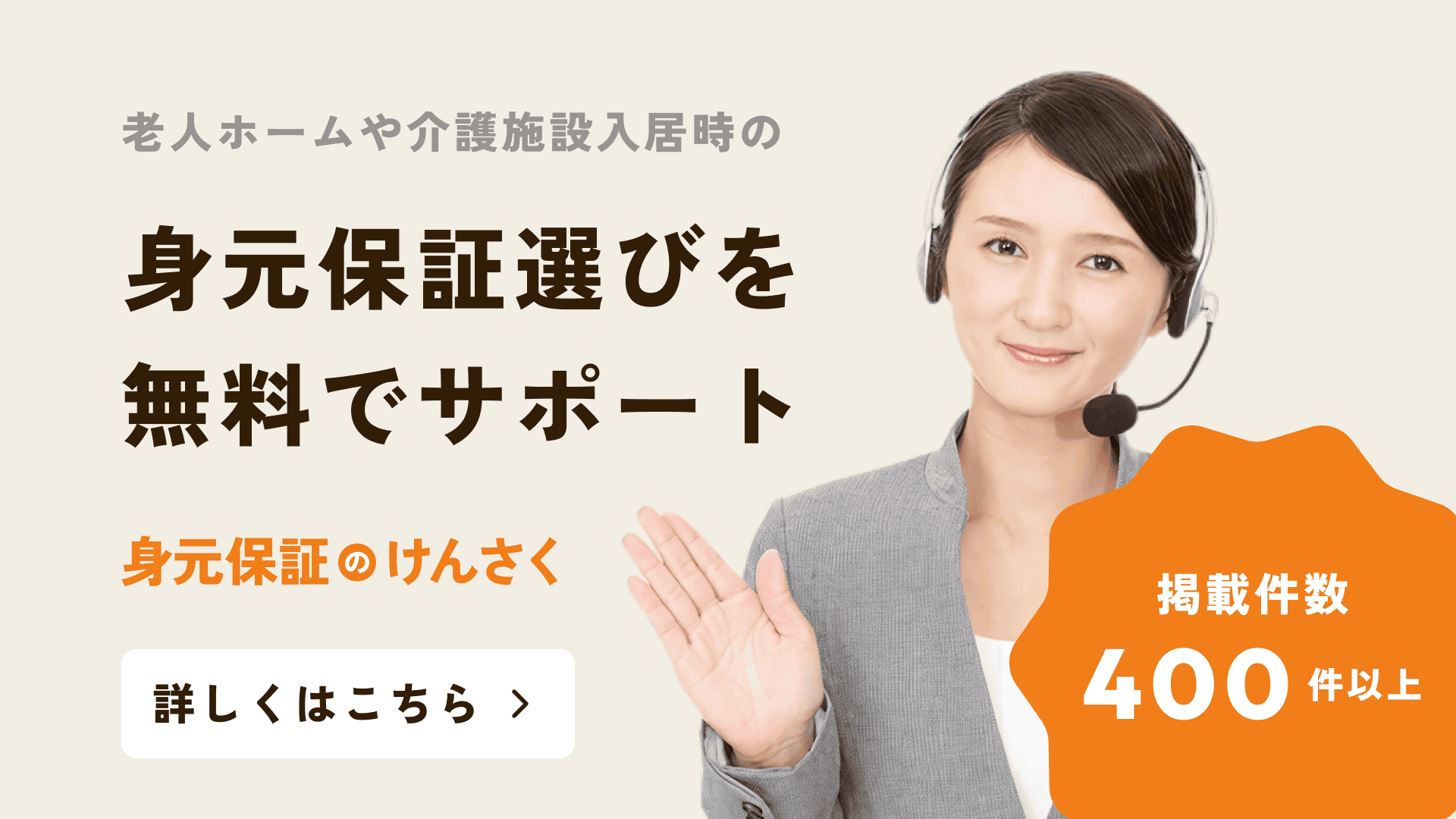
編集者プロフィール

身元保証のけんさく編集部
月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)